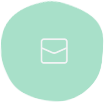木漆工芸作家が営む当店では、
漆の食器を使用して珈琲をお楽しみいただけます。

立ち上げたキッカケ
「美術館の中にいて、アート作家と会話のできるカフェ」を創りたいという想いから始まりました。
学生時代、美術館は人込みの中に行く、展示を見終わった後もどっと疲れると気が重くなりがちで、興味がある展示も億劫になりがちで苦手でした。
その時、座りながらゆっくり時間を忘れるように眺めていたいなっと思ったことがキッカケです。
また、日本には身近にアートが少なく、アートとの疎遠感も感じていました。
「カフェ」というアイテムを活用しながら、普段アートとの接点もない人もアートに触れられる空間を創りたい。
そして、美術館ではアート作家と対話をすることはほとんど叶いません。
アート作家と対話すると、その人がどんな気持ちで作品を作っているのか知ることができます。
自分で創る空間なら居心地のいい場所でアートと接したい、そんな想いを1つの空間で味わえる「Art Gallery Café 茶々華」を立ち上げました。
学生時代、美術館は人込みの中に行く、展示を見終わった後もどっと疲れると気が重くなりがちで、興味がある展示も億劫になりがちで苦手でした。
その時、座りながらゆっくり時間を忘れるように眺めていたいなっと思ったことがキッカケです。
また、日本には身近にアートが少なく、アートとの疎遠感も感じていました。
「カフェ」というアイテムを活用しながら、普段アートとの接点もない人もアートに触れられる空間を創りたい。
そして、美術館ではアート作家と対話をすることはほとんど叶いません。
アート作家と対話すると、その人がどんな気持ちで作品を作っているのか知ることができます。
自分で創る空間なら居心地のいい場所でアートと接したい、そんな想いを1つの空間で味わえる「Art Gallery Café 茶々華」を立ち上げました。

漆器制作にかけた想い
自分のアートを表現するのに、見て終わってしまうオブジェアートではなく、使ってアートになるものを作りたいという想いがあります。
漆器を選んだのは、「木」と「日常で使える豊かなもの」から選びました。
幼いころから木に関わる仕事がしたいと思っていて、大工さんから始まり、家具屋さん、伝統工芸士になりたい…とそんな人生を歩みながら、1浪して入った当時の東京藝術大学美術学部工芸科には木工芸が無く、木を触るには漆専攻に進むしかありませんでした。
漆かぶれも怖いし漆に進むのかもかなり悩みました。
制作工程を大学で学ぶと、もの凄い工程量を経た作品が美しすぎて魅了されていきました。
私自身も漆器に対して敷居が高い上に今の時代ほとんど使われていないと思っていました。
漆の文化を勉強している内に、下町の人たちにも広く日常的に使われていた食器だと気が付き、漆器文化をまたひと昔の日本の生活文化と同じくらい使われて欲しいという願望もあり漆器で自分の世界を表現したく、現在、漆器をメインに制作しています。
漆器を選んだのは、「木」と「日常で使える豊かなもの」から選びました。
幼いころから木に関わる仕事がしたいと思っていて、大工さんから始まり、家具屋さん、伝統工芸士になりたい…とそんな人生を歩みながら、1浪して入った当時の東京藝術大学美術学部工芸科には木工芸が無く、木を触るには漆専攻に進むしかありませんでした。
漆かぶれも怖いし漆に進むのかもかなり悩みました。
制作工程を大学で学ぶと、もの凄い工程量を経た作品が美しすぎて魅了されていきました。
私自身も漆器に対して敷居が高い上に今の時代ほとんど使われていないと思っていました。
漆の文化を勉強している内に、下町の人たちにも広く日常的に使われていた食器だと気が付き、漆器文化をまたひと昔の日本の生活文化と同じくらい使われて欲しいという願望もあり漆器で自分の世界を表現したく、現在、漆器をメインに制作しています。

漆器について
漆器は、敷居が高い・金額が高い・扱いずらそう、という3大マイナスイメージの強い食器です。
塗料にしている漆も年々高くなる一方ですし、工程量も多いのでどうしても値段が張りますが、漆器は普通に使っていても100年ものといわれるくらい孫世代まで余裕で使えます。
1万年以上前の漆の装飾品が日本で見つけられるほど塗料の世界では最古に分類され、何より天然の塗料なので、人外がありません。
今のご時世、塗料に対する表記の法律はなく、1%でも漆が入っていると漆器として売られてしまっているのが現状です。
残りの99%は石油を原料とした科学塗料です。
そういった塗料が普通に箸に塗られ、食事と一緒に体内に入り、微量とは言えど、長年の食事場面で体内に蓄積されていくわけですから安さに捕らわれず天然の食器を使ってもらいと切に思います。
カフェで使用する食器たちは、「ひと昔の日本の生活文化と同じくらい使われて欲しいという願望から、日常のいち場面にカフェがあるなら、茶々華の中だけでも漆器を日常化し漆器に対するハードルを低くしたい。
そして、科学物質の無い安心して飲食のできる空間のご提供をしています。
塗料にしている漆も年々高くなる一方ですし、工程量も多いのでどうしても値段が張りますが、漆器は普通に使っていても100年ものといわれるくらい孫世代まで余裕で使えます。
1万年以上前の漆の装飾品が日本で見つけられるほど塗料の世界では最古に分類され、何より天然の塗料なので、人外がありません。
今のご時世、塗料に対する表記の法律はなく、1%でも漆が入っていると漆器として売られてしまっているのが現状です。
残りの99%は石油を原料とした科学塗料です。
そういった塗料が普通に箸に塗られ、食事と一緒に体内に入り、微量とは言えど、長年の食事場面で体内に蓄積されていくわけですから安さに捕らわれず天然の食器を使ってもらいと切に思います。
カフェで使用する食器たちは、「ひと昔の日本の生活文化と同じくらい使われて欲しいという願望から、日常のいち場面にカフェがあるなら、茶々華の中だけでも漆器を日常化し漆器に対するハードルを低くしたい。
そして、科学物質の無い安心して飲食のできる空間のご提供をしています。